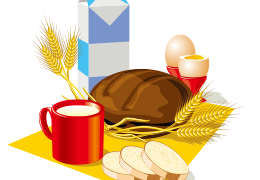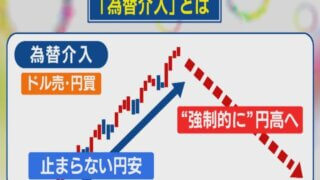トラスの辞任を市場は歓迎
英国時間20日午後。
トラス首相による辞意表明の観測が駆け巡った欧州市場では、英30年物国債利回りが下落(債券価格は上昇)、通貨ポンドは急上昇し「歓迎」の意を示した。
トラス氏は、英史上最短の就任44日で退陣に追い込まれた。
トラス政権が打ち出した大規模減税は財源の手当てがなく当面は借金に頼る計画だった。
インフレ退治の利上げを進めるなかでのやみくもな減税は、財政の急激な悪化を招き、経済成長の土台すら崩壊させかねない。
サマーズ元米財務長官など多くの識者が「最悪のマクロ経済政策」と批判した。
政権を実際に追い詰めたのが国債市場だ。財政悪化を見越し、金利上昇の警告を発してブレーキをかける市場機能は「債券自警団」と呼ばれる。
1990年代後半からの低インフレ時代になると、低金利が続き警告を発しなくなっていた。
インフレが再来して中銀が金利を抑圧できなくなった今、「債券自警団は再び解き放たれた」。
名付け親のエコノミスト、エド・ヤルデニ氏はこう指摘する。
新型コロナウイルス禍への対応では金融緩和と財政出動が望まれたが、インフレで環境は変わった。
安易な借金が危険な時代になったことを認識せずにいると市場に拒絶される。
日本の長期金利の理論値は1.5%
日本の国債市場はというと、なお別世界にある。
日銀の「管理下」にあり、長期金利は0.25%以下に抑え込まれている。
10月の最初の10営業日のうち長期金利の指標となる新発10年物国債の取引が成立したのは半分の5日のみ。
市場機能は極端に低下している。
債券自警団は警告を発しない。そのため、低金利時代の発想に安住しているかのような動きがみられる。
「真水で30兆円の財政出動が発射台だ」(自民党の世耕弘成参院幹事長)。
政府が10月末にまとめる経済対策を巡って、与党幹部からはなお規模重視の発言が相次ぐ。
政府はコロナ禍以降、すでに100兆円以上の赤字国債を発行し財政を膨らませてきた。
新たな経済対策では円の下落に伴うガソリン価格の上昇などを補助金で賄う。
ひずみは着々と蓄積している。ニッセイ基礎研究所が日銀のマイナス金利政策や長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)など各政策でどの程度、金利を抑えているかを試算し、10年物国債利回りの理論値を出したところ9月末時点で1.5%台となった。
日銀が上限とする0.25%より1.3%ほど高い。

このひずみが円安圧力となっている。
「物価上昇などに応じて上がるべき金利が低く抑えられ、米国との金利差が拡大しやすくなっている分、円安を増幅している」(ニッセイ基礎研の福本勇樹金融調査室長)
物価上昇率は英国の10%に対して日本は3%。
金融緩和と財政拡張を続けても直ちに危機になるわけではない。
ただ、円安が一段と加速してインフレが本格化し、日銀が金利を抑圧できなくなれば財政への懸念が噴出しかねない。
ピクテ・ジャパンの市川真一シニア・フェローは「財政と金融のもたれ合いを打ち切らない限り、円安を構造的に止めることはできない」と指摘する。
米金利上昇を主因とした円売りが「日本売り」に転じるリスクはないのか。
円安は「通貨」自警団による警告の様相を帯びている。