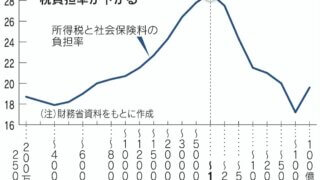このオフ、日本人選手の米大リーグ移籍が相次いだ。
今回、注目したいのはその契約額だ。
メッツに入団する千賀滉大(前ソフトバンク)は5年総額7500万ドル、レッドソックスに移籍する吉田正尚(前オリックス)は同9000万ドルといずれも日本円にして100億円規模、年俸にして20億円前後となった。
アスレチックスに加入する藤浪晋太郎(前阪神)は325万ドル、出来高も入れると最大425万ドルでの契約だ。
2022年、日本での3人の推定年俸は千賀が6億円、吉田が4億円、藤浪は4900万円だった。
1ドル=130円で換算すると、大リーグでの報酬は千賀がおよそ3倍、吉田が6倍、藤浪が出来高なしでも9倍近くということになる。
千賀と吉田はリーグを代表する実力者だったが、藤浪は直近3年で計7勝しかしていない。
阪神で1軍の戦力にもなり切れなかった選手に米国でこれだけの値がつく現実は、何を示しているのだろうか。
米経済誌フォーブスの電子版は10日、米大リーグの22年の総収入が108億ドル(約1兆4250億円)を超え、19年の107億ドルを上回って過去最高になったと伝えた。
108億ドルを単純に30球団で割って日本円に換算すると、1球団当たりの収入は約470億円となる。
日本でトップレベルの収益力を誇るソフトバンクの22年2月期の売上高は237億円だから、メジャーは平均で2倍の収入があることになる。
そのうえ球場の利用条件なども日本より優遇されているので、選手への配分比率を高めても採算が合う。
AP通信によると、22年の大リーグの総年俸は45億6000万ドル。
前年より約13%も増加し、過去最高だった17年を7%も上回り、史上最高を更新した。
大谷翔平(エンゼルス)の23年の年俸は3000万ドル。
日本プロ野球選手会の調査では、古巣の日本ハムは22年の支配下選手の年俸総額が約17億円だから、チーム全員を合わせたよりもはるかに高い額を1人で稼いでいることになる。
メジャーは下部組織の選手の年俸も負担しているため、支払い対象は日本以上に大きい。
年俸増加の一因はマイナーリーガーの待遇改善などもあるが、収入の増加を考えれば選手の取り分は現状でもまだ十分ではなく、もっと高くていいという意見もある。
大リーグは近年、観客動員の減少が続いている。
新型コロナウイルスによる打撃も追い打ちをかけ、22年の観客数はコロナ直前の19年に比べて6%少なかった。にもかかわらず、収入はなぜこれほど伸び続けているのだろうか。
増収をけん引するのは球場外での売り上げだ。
22年の放映権料は前年より2億5000万ドル増えて17億6000万ドル、スポンサー契約料は前年比約6%増で11億9000万ドルとなった。
メジャーでは全国放送の放映権は米大リーグ機構(MLB)が一括管理しており、各球団には70億~80億円規模の分配金が入る。
ある球団の関係者は「ベッティングを解禁する州が増え、球場や周辺施設でこれを提供する球団も出てきている。リアルタイムで賭けの対象になることでコンテンツの需要がさらに高まり、放映権料の上昇は続くのでは」という。
放映権料で稼ぐ大リーグとは対照的に、日本のプロ野球は集客を軸としたライブエンターテインメントとして成り立ってきたため、新型コロナの打撃は大きい。
日本人選手の相次ぐ高額契約は日米球界の経済格差が拡大している証左にほかならない。
同じ規格のホテルのシングルルームでもニューヨークと日本の地方都市では値が大きく違うように、選手の相場が別次元になってしまったのだ。
日本球界にとって、これは悩ましい現実である。
大リーグが一部のエリート選手にしか興味を示さなければ、それほど神経質になることはないのかもしれない。
しかし、ここ数年低迷していた藤浪にも米国で需要があり、移籍できれば日本のトップ選手以上の年俸を得られるとなれば、話は変わってくる。
ラジオに出ていたタレントが、テレビに出れば同じ時間と労力で何倍ものギャラがもらえると知れば、テレビ志向になるのはやむを得ない。
同様にレギュラークラスの選手にまで米国志向が広がれば、日本はメジャーへ行くための「腰掛けリーグ」になりかねない。
日本の野球のレベルが下がっているからではなく、上がっているゆえにこうした現象が起きているのは皮肉なことだ。
ビジネスとしてのうまみがある大リーグには次々と新たなプレーヤーや資金が集まり、ますます裕福になる。
一方、新陳代謝が乏しい日本球界は事業モデルも各球団の裁量が大きく、リーグ全体で稼ぐ構造になっていない。
即効薬があるわけではないが、大リーグをモデルにして、リーグの価値を高める策はあるはずだ。
危機感を強めている球界関係者は少なくない。
メジャー並みとはいわないまでも、日本でも球団や選手が十分と感じられる収益や年俸を得られる形を模索してもらいたい。